「子どもの様子が変。元気がない」、「学校に行きたがらない」、「理由を家族にも話したがらない。コミュニケーションも減った。」、「不登校が長期化しつつあり悩んでいる」など、さまざま程度の差はあれ、子どもさんの不登校についてお悩みではありませんか。
子供を励ましたり元気づけようとかけた言葉が、逆に子どもを追い詰めてはいないか、子どもの日々の体調や表情に気を配りながら寄り添っているつもりでもうまくいかない。 そんな悩みを抱えながら過ごしていらっしゃる親御さんがたくさんいらっしゃるいます。
小・中学校における不登校児童生徒数は全国で346,482人、高校生の不登校生徒数も68,770人といずれも過去最多となりました。
また、小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数も732,568件で過去最多となるなど、子どもたちを取り巻く環境は大変厳しくなっています。
(R6.10.16 文部科学省調査資料)
こうした現状は知りつつも、不登校になっている子どもさんへの心理的アプローチについては、これといって決定的な対策法がないのが実情だと思います。
今回は、そうしたお悩みに少しでもお役に立てるよう、具体的なアドバイスをお伝えしようと思います。
”子ども と 自分” を信じてあげること
まず大切なこと。それは、子どもとそれに関わる親(自分自身)を信じることです。
不登校になった途端にほぼ全ての親御さんは慌ててうろたえます。当然、「愛情を持って我が子を育ててきたつもりなのに。うちの子がなぜ?」、「よその子は今日もふつうに学校に通えているのに、なぜ我が子は行けないの?」という気持ちが湧き上がってきます。
特に初期のころはそう思いがちですが、初期こそ冷静に現状を見据え、落ち着いて子どもに向き合える親であることが大切です。
不登校の要因は子ども一人ひとり違いがあり、一様に対応することができません。子どもなりに学校に行かない選択をしているわけですから、重大な決心をしているはずです。その理由については一言二言の会話で説明できるものではありません。
子どもさんなりに、学校生活あるいは友人関係のトラブルなど日々のストレスが積み重なって、心のエネルギーが枯渇した可能性もあります。また、それ以外でも、家庭内の不和などいくつかの不安要素が複雑に絡んでいるケースもあります。
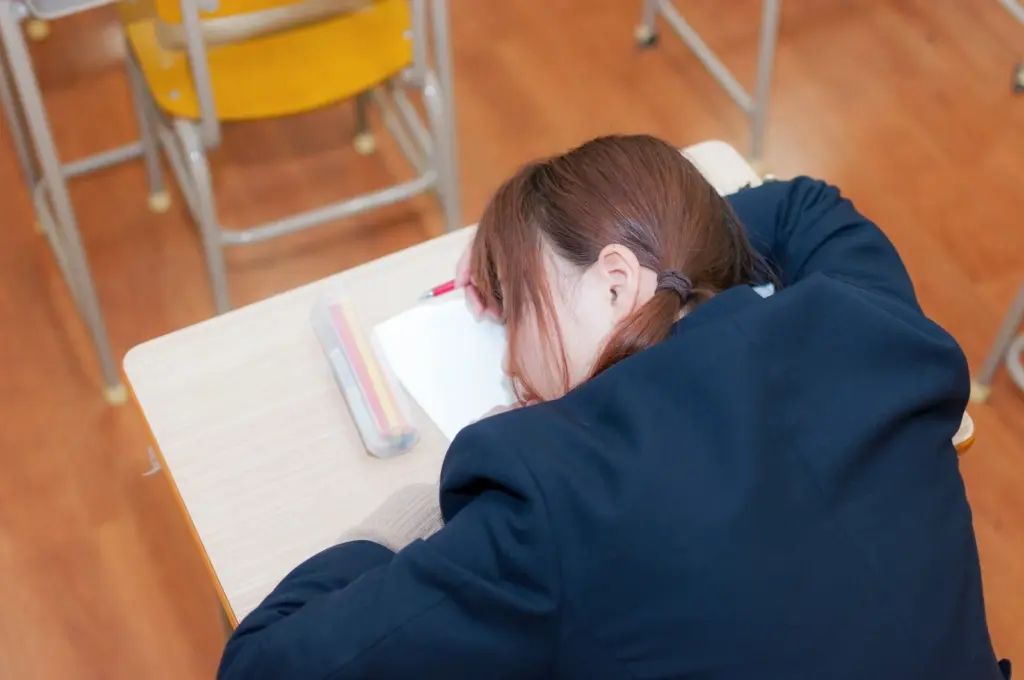
子どもは、自分の気持ちを順序だてて細かく説明する能力がまだ備わっておらず、ましてや一番身近な親にストレートに悩みを打ち明けることが苦手です。また、子どもは、”自分のことで親に迷惑をかけたくない”という気持ちも強いのが事実です。親が不安顔で無理やり理由を問いただしたり、激励するのは逆効果になる可能性があります。
そうした点を踏まえ、親は、「子どもも自分なりに頑張って学校生活を送ってきたに違いない。だからこそ心も体も疲れてしまうこともあるだろう。疲れて休みたいというのは当然かもしれない」と冷静に構え、少しずつ子どもの考えを聞いてみることが大切です。
親自身が落ち着いて、「これまでも色んな悩みを乗り越えて子どもを育ててこれたんだ。きっとこれからもうまくいく。子どもと対話しながら対策を練っていこう。」というふうに自分を肯定していくことが、良い結果を生みます。
子育てに関して発想を変えてみる良い機会ととらえる
先ほどは、子どもさんが学校に行かず家にいるという決心をしたのには何か理由があるはずで、その原因探しを急ぎ過ぎるとよくないとお話ししました。
もしかしたら子どもが誰かにいじめられているのでは、あるいは、自分の育て方が良くなかったのではと次々と不安が起こるのは無理もありませんが、ここで発想の転換を図ってみるのもいいかもしれません。
不登校になると、子どもは家で過ごす時間が多くなります。子どもが強く行き渋りを示す場合は、自然な形で家での生活を見守り、時にはお手伝いや会話を促し、コミュニケーションをとる機会を増やしましょう。
子育ては、悩み・不安の真っただ中にいるときは長く感じますが、アッという間に子どもは親の元を離れていくものです。
子どもが家にいる時間が多くなったということは、子どもとより深い会話ができて、子どもの本心に触れられる機会も増えるということになります。
”家”という安全基地で”自分”をとりもどす
安心できる”居場所”を確保する

どんな人も自分が落ち着ける場所、”居場所”が必要です。それが本来の「家」であり、ありのままの自分を受け入れてくれる場所、構えずに本心が話せる場所であるならば、人は基本的に大丈夫です。
子どもが、学校に行くより家で過ごすことを選んでいる以上、家をそうした空間にしていくことが大切です。
もちろん家族という身近な存在ゆえ、心がすれ違い、ケンカになることは多々あります。でも、それを乗り越えた先に深い理解が生まれます。子どもとは根気強くコミュニケーションをとっていきましょう。
また、家で本人ができることは全てやらせてあげましょう。勉強ではなくても、手伝いでもなんでも良いのです。本人に誰かの役に立っているという感覚を持たせることが大切です。
なお、大前提として、学校に行かないこと自体が決して悪いことではないことをしっかり伝え、今は安心できる”家”で、これからのことをゆっくり話し合える雰囲気を作っていくことが重要です。
ほかの人と比べない ”自分の生き方、ペース”を守る
不登校数が増えたとはいっても、本人の気持ちは「友達は行けているのに、私はダメだ」とか「○〇君でさえ行けてるのに…」という 取り残され感や 劣等感を強く感じることもあります。
親としては、子どもが自分自身を信じる力を失わないよう、「○〇君は○〇君、 あなたはあなた。一人ひとり皆違っていい」、「あなたの○〇○なところが、お母さんは好き」、「やりたいことがあれば応援するよ」といった前向きな言葉かけをしていきましょう。
では、もし子供が「自分はだらしない性格だから嫌いだ」、「何をやっても集中力がないし、勉強もできないし」、「もう、どうなってもいい」とマイナスの思いを口に出しはじめたらどうすればいいのでしょう。
そういった時は、子ども自身が自分のことを表現できたことを褒めながら、どんな時も親として応援していくことを伝え、次のステップにつながるアドバイスをしてあげればいいのではないでしょうか。
例えば、「自分の思いを正直に伝えてくれてありがとう」、「自分のそういう性格が嫌いなんだね」、「でも、それは自分が”嫌い”なだけで、決して”悪い”というわけじゃないよ」、「あれこれ考えたり、色々やって集中できないってことは、何かひとつでもいい、自分の大好きなことに打ち込んでみたらどう?」といった声かけはどうでしょう。
一例ではありますが、あれこれ考えていくことに意味があります。

誰しも完璧な人はいない
不登校問題については、子どもさんはもちろん、親御さんもこれまでの子育てを振り返り、大きな不安や焦りに押しつぶされそうになるかもしれません。
「自分の子育てに至らないところはなかっただろうか?」、「もう少し愛情深く接すればよかったのでは?」「いろいろ子どもに不自由をかけてしまったのでは?」と過去を振り返り、未来については「このままずっと外に出られずにいたらどうしよう…」など、自分を否定し続けることで、心身の不調まで引き起こしてしまいそうです。
人は過去や未来に対して、後悔、不安といった感情を抱きます。でも言えることは、目の前の現実に向き合い、できることをやるしかないのが現状です。
もともと完璧な人は誰もいません。そして、人間の心を癒し治すことに明確な正解はありません。なのでやってみては修正、またやってみては修正、そういった思いで臨むことが大切です。

※ 不登校の悩みを相談できる主な窓口や専門機関については、お住いの地域によって異なりますが、おおむね下記の機関が相談に応じてくださいます。
それぞれの特徴、効果的な活用方法についてはそれぞれの機関にお尋ねください。抱えきれない問題の解決のためには、積極的に社会制度をうまく利用していきましょう。
《不登校やいじめ、ひきこもりなどの相談窓口》
市町村教育支援センター、スクールカウンセラー(教育委員会)、児童家庭支援センター、児童相談所、ひきこもり地域支援センター、発達障害者支援センター、フリースクール(民間)、 24時間子どもSOSダイヤル(文部科学省)、不登校支援団体(NPO等)など



コメント